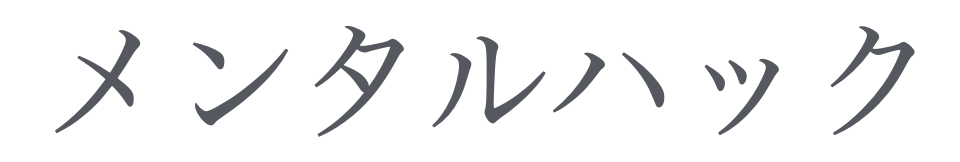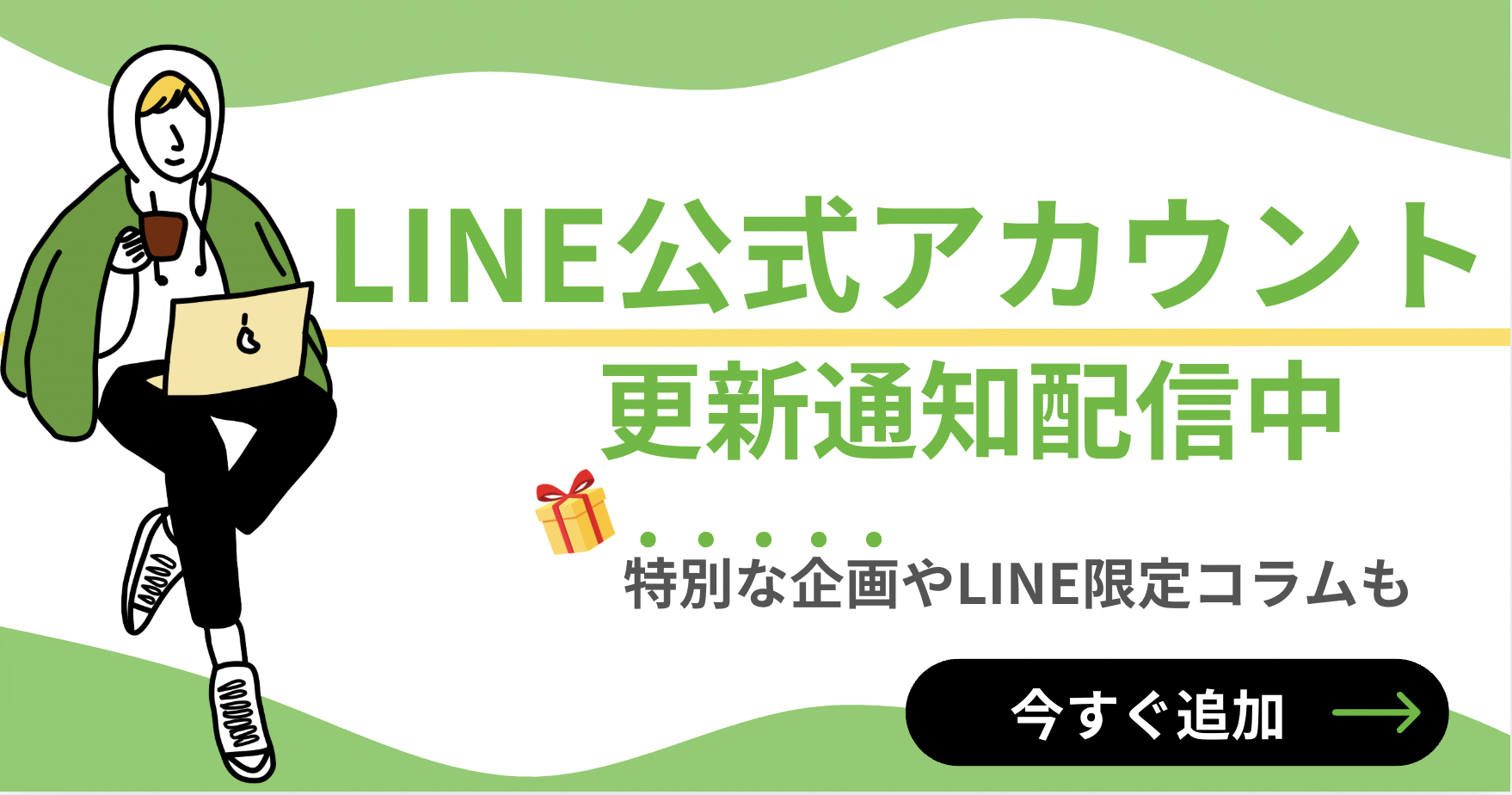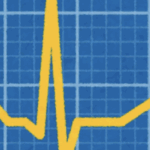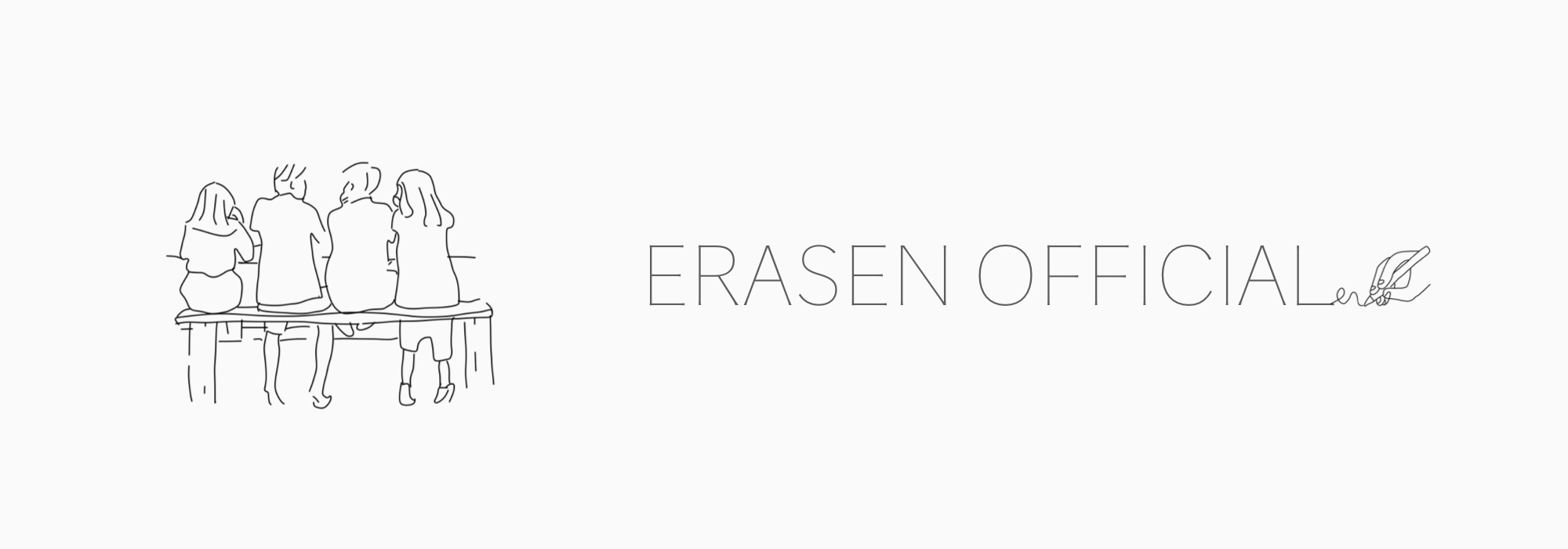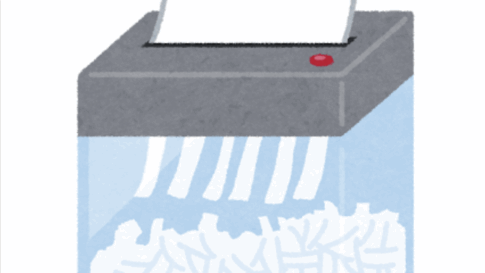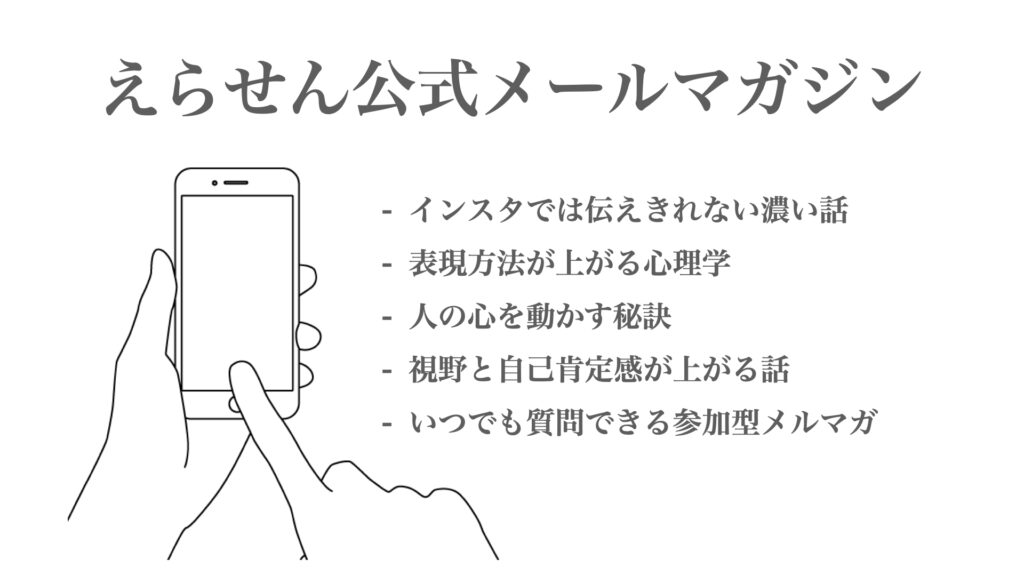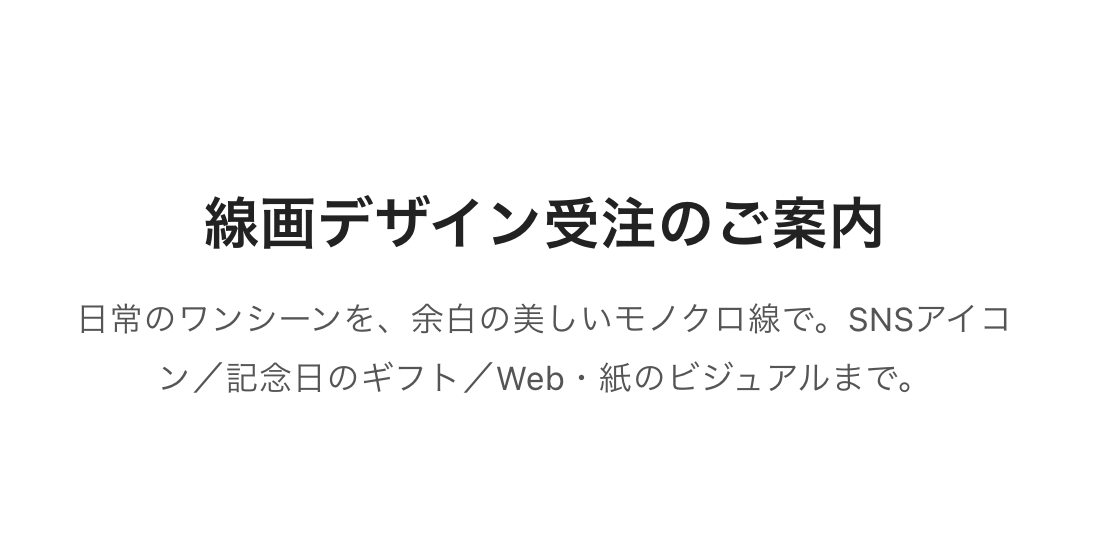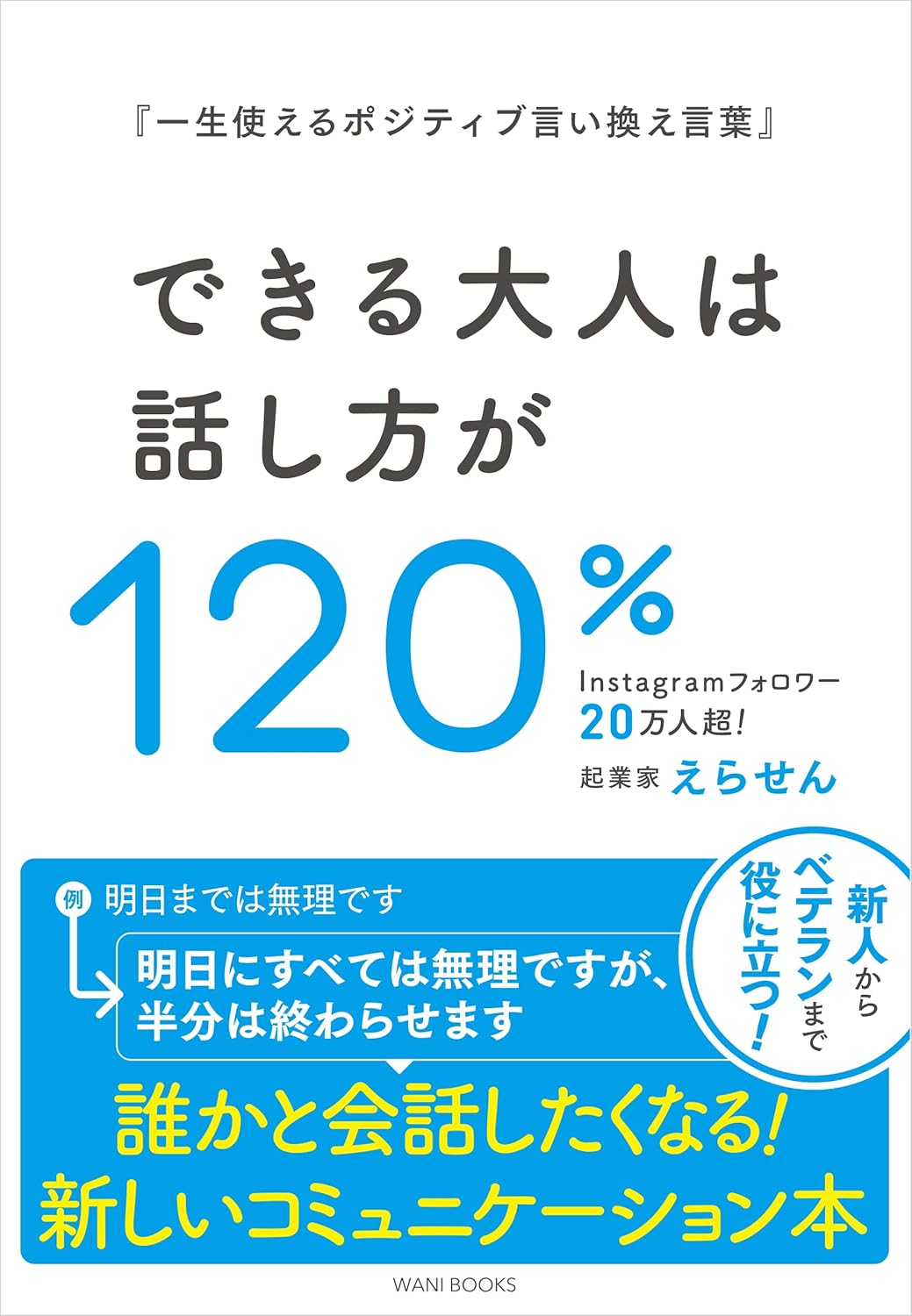こんにちは、えらせんです。
今回は「なぜ勉強をしないといけないのか」というテーマで話していきます。「勉強なんて意味あるの?」と思っていたあの頃の僕に、いまならこう伝えたい。教科書の中には、人生の土台になるヒントがたくさん詰まっていたんだって。
目の前の科目に「将来使わないじゃん」と思うのは自然なこと。でも、科目の“本質”を知れば、それは「使わない知識」じゃなくて、「人生に応用できる考え方」に変わっていきます。ひとつずつ、解説していきますね。
① 国語 → 誰かの本音に気付けるようになりなさい
読解力というのは、ただ文章の意味を取る力ではありません。行間を読み、言葉にされていない「本心」や「背景」を察する力です。誰かのメッセージに潜む「本当はこう思っているのかも」というサインを拾える人は、人間関係でもトラブルが少なく、信頼されやすくなります。だから国語は、“人の気持ちを読み取る力”を育てる訓練なんです。
② 数学 → 本質を見抜く目を養いなさい
公式を覚えるだけでは意味がありません。大切なのは、「物事の仕組みやパターン」を見抜く力を身につけること。複雑に見える問題も、一歩引いて見れば、シンプルな構造でできていたりする。それに気づける目を養うことが、仕事でも人生でも役に立ちます。数学は、“表面に惑わされずに本質を見抜く”目を育ててくれる教科です。
③ 家庭科 → 誰かをそっと支えられる人になりなさい
料理や裁縫だけじゃない。家庭科の本質は「暮らしの中での思いやり」です。誰かが心地よく過ごすために、どんな工夫ができるか。「これがあると助かるかな」と想像できる人は、人を自然に癒せる人です。支えるって、大きなことじゃなくていいんです。気づかれないくらいの優しさで、そっと寄り添える人ってすごくかっこいい。
④ 理科 → 仕組みを知って考えを深めなさい
理科は、「なぜ?」の答えを探す学問です。身のまわりの出来事の裏側には、必ず“仕組み”がある。
原因と結果の関係を理解できるようになると、感情に流されずに冷静に判断できるようになります。理科は、“物事を深く理解するための視点”をくれる教科なんです。
⑤ 社会 → 歴史から学び、未来を読みなさい
人間は、過去から学ばないと同じ失敗を繰り返します。歴史を学ぶことで、「今この状況は、過去のあれと似てるな」と気づく力がつきます。地理や政治経済も、今のニュースを“自分ごと”として考えるための武器になります。社会は、“未来を予測するための地図”をくれる教科です。
⑥ 英語 → 世界とつながる力をつけなさい
英語を話せる=かっこいい、ではなく、「違う価値観の人とコミュニケーションが取れる」ことが、本当の意味です。日本だけで完結しない時代だからこそ、自分の考えを外に届けたり、外の考えを柔軟に受け入れる力が必要になってきます。英語は、“世界と橋をかける言葉”なんです。
⑦ 道徳 → 見えない傷に気付ける人になりなさい
「正しさ」を学ぶだけでは足りません。誰かが傷ついているとき、声に出せなくても察してあげられること。「相手の立場に立って考える」という想像力が、何よりも大切です。道徳は、“思いやりという名のセンサー”を磨く教科です。
⑧ 美術 → 自分を表現する術を見抜きなさい
「絵が上手いかどうか」は本質ではありません。自分の感情を、色や形でどう表すか。内面を外に出す方法を知っている人は、自分を押し殺さずに生きることができます。美術は、“言葉じゃなくても自分を伝える力”をくれる教科です。
まとめ
どの教科も、「いい点を取るため」にあるんじゃない。自分の世界を広げてくれる、大切な“入り口”です。「なんのために勉強するの?」って悩んだときは、ぜひ、この記事を思い出してみてください。
次回はもっと面白い記事を書くので、お楽しみに!
そして、ここだけの話ですが…
実は「自己肯定感ブートキャンプ」というサービスもやっています。自己肯定感を底上げし、恋愛や仕事など人生全体を前向きに変えていくためのサポートの場です。
もし興味があれば、ちらっと覗いてみてください。
▶︎https://sb.eraisensei.com/p/Oi1ZCw6bNZbk/KSLUgHbSThQz